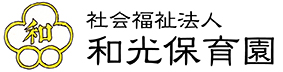今月の徳目は「忍辱持久」(辛い時が来ても逃げることなく受け止めていこう)です。
現代の世の中にあって、「がまんすること」を子どもたちに教えることは、大切なことであると同時にとても難しいことです。なぜなら、具体的な場でがまんしなければならないことが少なく、どんなことでもある程度お金で解決できてしまうので、がまんが満たされやすいことが多いからだと考えられます。
しかし、「がまんすること」ができない子どもは、わがままな子どもになり社会性の発達が遅れていくのです。このようなことを考えると「がまんする」「耐える」ということは教えていかなければならないことだと言えます。お釈迦さまもいろいろな場面で耐え忍ぶことを教えられています。
ある日、お釈迦様の子どもラゴラが強盗に会い、頭を殴られてしまいます。歯を食いしばってこらえているラゴラの頭からも血が流れています。「どんなことがあっても怒ってはいけない。心を抑えて耐え忍ぶことこそお釈迦様の教えを守る勇気ある行動なのだ」と自分に言い聞かせて耐え抜いたのでした。お釈迦様はその話を聞いて「もし忍ぶことを知らない人がいたらその人は仏に会うことができないであろう。私が安らかな暮らしができるのも忍のおかげである」と説かれたのだそうです。命の危険を感じながら耐え忍ぶラゴラの姿にはとても厳しいものを感じます。お釈迦さまも悟りをひらくために様々な障害や誘惑に耐え、それを乗り越えたことを考えるととてもたいへんだったことだとおもわずにはいられません。忍ぶことには勇気がいります。
このことを今の子どもたちにどこまで話して、理解してもらうかはとても難しいことだとは思いますが、「耐えること」や「忍ぶこと」の必要性を説く一つの話にはなるのではないでしょうか。
※佛教保育なるほど12ケ月より引用 文責;園長 白井 千晴
|
仏教保育なるほど12ケ月 |
辛夷の木に新しい芽が芽吹きました |