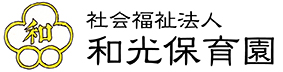今月の徳目は「報恩感謝」(社会や自然の恵みに感謝しよう)です。
人間は、自然や社会の様々なつながりをもって、初めて生活できているのです。私たちが普段から当たり前のように食べているものも、太陽や水、大地、といった自然やそれを作る農家の人々や運搬する人、販売、調理する人々など様々な人の手を経て初めて食べることができるのです。食べ物以外にも、衣服や住居、学校や保育園、社会なども様々な人たちのおかげで成り立っているのです。また、子どもたち自身もその社会の一員であることを気づかせています。
こういった自然や社会の恵みに気付き、感謝の気持ちをもって日々の生活を送りたいものです。子どもたちに感謝の気持ちが育つにはどうしたらよいのでしょう。それは、子どもたち自身が誰かから感謝の気持ちを伝えてもらうことだと考えます。自分がされて気持ちがよいことだと分かると自然と他人にも感謝の気持ちをもつことができるのではないでしょうか。そのためには、お手伝いやお当番をやるのも一つです。誰かのために働くことがいつかは自分に返ってくるものです。これを繰り返すことで子どもたちに感謝の気持ちが育ち、お互いが助け合い、支え合って生きていることを感じ「ありがとう」「おかげさま」「おたがいさま」という言葉が自然と出るようにしたいですね。
(仏教保育なるほど12ケ月 参照) 文責;園長 白井 千晴